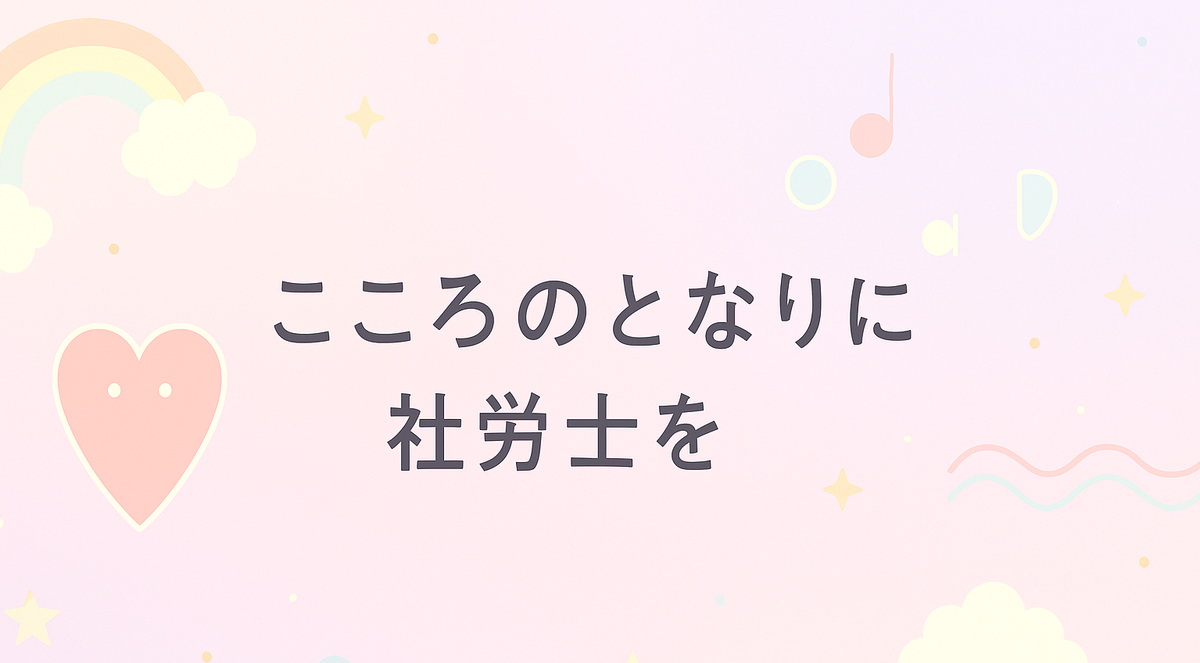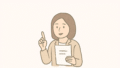「就労移行支援って、実際にどんなことをするの?」 「2年間で本当に就職できるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。今日は、就労移行支援の利用開始から就職、そして定着支援までの流れを、段階ごとに詳しく説明します。
全体の流れ(2年間のスケジュール)
就労移行支援は、一般的に以下のような流れで進みます。
利用開始前(1~2ヶ月) ↓ アセスメント期間(1~2ヶ月) ↓ 基礎訓練期間(3~6ヶ月) ↓ スキルアップ期間(6~12ヶ月) ↓ 就職活動期間(3~6ヶ月) ↓ 就職・定着支援(6ヶ月)
合計:約24ヶ月(2年間)
ただし、これはあくまで目安です。一人ひとりのペースに合わせて進めていくので、早く就職する方もいれば、じっくり準備する方もいます。
【STEP1】利用開始前の準備(1~2ヶ月)
相談窓口への問い合わせ
まずは、どこに相談すればいいのかを知ることから始まります。
相談先
- 市町村の障害福祉担当課
- 相談支援事業所
- ハローワークの専門援助部門
- 障害者就業・生活支援センター
「就労移行支援を使いたいのですが…」と伝えれば、丁寧に説明してもらえます。
事業所の見学・体験
複数の事業所を見学することが大切
最低でも2~3ヶ所は見学しましょう。事業所により雰囲気や訓練内容が全く違います。
見学時のチェックポイント
- 利用者の雰囲気(明るいか、集中しているか)
- スタッフの対応(親身か、専門的か)
- 訓練内容(自分の希望に合っているか)
- 施設の清潔さ・設備
- 通いやすさ(交通アクセス)
体験利用をしてみる
1~2日間の体験利用ができる事業所が多いです。実際に訓練に参加してみることで、自分に合うかどうかが分かります。
申請手続き
必要な書類
- 障害者手帳または医師の診断書
- 所得証明書(利用料の決定に必要)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- その他、市町村指定の書類
受給者証の交付(2~4週間)
市町村が審査を行い、問題なければ「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
【STEP2】利用開始~アセスメント期間(1~2ヶ月)
初日の緊張
利用初日は、誰でも緊張するものです。
初日の流れ
- オリエンテーション(施設のルール説明)
- スタッフ・他の利用者との顔合わせ
- 簡単な作業やプログラムの体験
- 今後のスケジュール確認
「思っていたより和やかな雰囲気で安心しました」という感想をよく聞きます。
アセスメント(評価)の実施
最初の1~2ヶ月は、現状の把握が中心です。
評価される項目
- 基本的な生活習慣(時間管理、身だしなみなど)
- コミュニケーション能力
- 作業能力(正確性、スピード、集中力)
- パソコンスキル
- 体力・健康状態
- 希望する職種や働き方
様々な方法でアセスメント
- 作業を通じた観察
- 面談での聞き取り
- 心理検査や適性検査
- 実際の作業場面でのチェック
個別支援計画の作成
アセスメントの結果をもとに、一人ひとりに合わせた「個別支援計画」を作ります。
計画に含まれる内容
- 2年間の目標(どんな仕事に就きたいか)
- 短期目標(3ヶ月、6ヶ月ごと)
- 必要な訓練内容
- 支援の方法
- 本人・家族の希望
この計画は、定期的に見直しながら進めていきます。
【STEP3】基礎訓練期間(3~6ヶ月)
生活リズムの確立
まず大切なのは、規則正しい生活リズムです。
基本的な訓練
- 決まった時間に起床する
- 毎日通所する習慣をつける
- 体調管理を意識する
- 疲労のコントロールを学ぶ
「最初は週3日通所するのも大変でしたが、3ヶ月経つ頃には週5日通えるようになりました」という方も多いです。
ビジネスマナーの習得
社会人として必要な基本的なマナーを学びます。
学ぶ内容
- 挨拶・言葉遣い
- 電話応対
- 来客対応
- 報告・連絡・相談(ホウレンソウ)
- 身だしなみ
- 時間管理
ロールプレイなどを通じて、実践的に身につけていきます。
基礎的なスキル訓練
パソコン訓練
- タイピング練習
- Word(文書作成)
- Excel(表計算)
- PowerPoint(プレゼン資料)
- メールの書き方
軽作業訓練
- 書類の仕分け・ファイリング
- データ入力
- 梱包・組み立て作業
- 清掃作業
コミュニケーション訓練
- グループワーク
- プレゼンテーション練習
- 自己紹介の練習
- 相手の話を聞く練習
この時期によくある課題
体力が続かない → 休憩を多めに取りながら、徐々に活動時間を延ばす
人とのコミュニケーションが難しい → まずは少人数から、段階的に慣れていく
集中力が続かない → 短時間の作業から始めて、少しずつ延ばす
焦らず、自分のペースで進めることが大切です。
【STEP4】スキルアップ期間(6~12ヶ月)
専門的なスキル訓練
希望する職種に応じた、より専門的な訓練を行います。
事務職希望の場合
- Excel関数の習得
- 書類作成の実務訓練
- データベース入力
- 電話応対の実践
製造・軽作業希望の場合
- 品質管理の方法
- 安全作業の習慣
- チームワークの実践
- 効率的な作業方法
サービス業希望の場合
- 接客マナーの徹底
- レジ操作訓練
- 清掃技術の向上
- クレーム対応の練習
企業見学
実際の企業を訪問し、働く現場を見せてもらいます。
見学の効果
- 働くイメージが具体的になる
- どんな配慮があるか分かる
- 自分に合う職場環境が見えてくる
- 就職への意欲が高まる
「実際の職場を見て、『自分にもできそう』と思えました」という声をよく聞きます。
自己理解を深める
自分の強みと課題を知る
- 得意な作業・苦手な作業
- 長く集中できる環境
- 疲れやすい時間帯
- ストレスを感じる場面
障がい特性への理解
- 自分の障がいをどう説明するか
- どんな配慮が必要か
- どんな工夫で乗り越えられるか
これらを言語化できることが、就職活動でとても重要になります。
グループ活動
様々なプログラム
- 話し合い活動
- 共同作業
- イベントの企画・運営
- プレゼンテーション
チームで協力する経験を通じて、コミュニケーション能力を高めます。
【STEP5】就職活動期間(3~6ヶ月)
履歴書・職務経歴書の作成
何度も書き直しながら完成させる
- 自己PRの作成
- 志望動機の整理
- 職歴の書き方
- 障がいの開示方法
スタッフと一緒に、何度も添削を重ねて仕上げます。
面接練習
繰り返し練習することが大切
- 入室・退室のマナー
- よくある質問への回答
- 自己紹介の練習
- 逆質問の準備
ビデオ撮影して自分の様子を確認したり、模擬面接を何度も行います。
「最初は緊張で何も話せませんでしたが、10回目の練習ではスラスラ話せるようになりました」
企業実習(インターンシップ)
実際の企業で働く体験
期間:通常1~2週間
実習の目的
- 実際の仕事を体験する
- 企業と本人の相性を確認する
- 必要な配慮を具体的にする
- 自信をつける
実習先でそのまま採用が決まることも多いです。
ハローワークでの求職活動
専門援助部門を利用
スタッフと一緒にハローワークに行き、求人を探します。
活動内容
- 求人検索
- 応募書類の提出
- 面接日程の調整
- 面接への同行(必要に応じて)
この時期の心の動き
不安と期待が入り混じる
- 「本当に就職できるのかな…」
- 「面接で落ちたらどうしよう」
- 「でも、働けるようになりたい」
こうした気持ちは、誰もが持つものです。スタッフや他の利用者と話しながら、前に進んでいきます。
【STEP6】就職決定
内定をもらった時
喜びと不安が同時に来る
「やった!就職が決まった!」 「でも、本当にちゃんと働けるかな…」
この複雑な気持ちは、とても自然なことです。
就職前の準備
企業との最終確認
- 勤務時間・曜日
- 業務内容
- 必要な配慮
- 通勤ルート・方法
- 緊急連絡先
事業所でのサポート
- 初日のシミュレーション
- 不安な点の整理
- 配慮事項の文書化
- 緊急時の対応確認
利用者の声
「2年前は毎日家にいて、外に出るのも怖かったのに、今は会社で働いています。信じられない気持ちです」
「何度も心が折れそうになりましたが、スタッフや仲間に支えられて、ここまで来られました」
【STEP7】就職後の定着支援(6ヶ月)
就職がゴールではない
就労移行支援の本当の目標は、「就職すること」ではなく「働き続けること」です。
定着支援の内容
定期的な面談
- 月1~2回、スタッフと面談
- 職場での様子を聞く
- 困りごとがないか確認
- 必要に応じて対策を考える
企業訪問
- 職場でのスタッフ訪問
- 上司との情報共有
- 働きぶりの確認
- 配慮事項の調整
緊急時の対応
- 体調不良時の相談
- 人間関係のトラブル相談
- 業務上の困りごと
- メンタル面のサポート
よくある定着支援の場面
仕事が覚えられない → メモの取り方を工夫する、マニュアルを作ってもらう
人間関係で悩む → コミュニケーション方法を一緒に考える、上司に相談する
疲れが溜まってきた → 休憩の取り方を見直す、勤務時間を調整する
6ヶ月後
定着支援が終了しても、多くの事業所では相談に応じてくれます。
「困った時はいつでも連絡してくださいね」
そんな言葉が、大きな安心につながります。
途中で辞めたくなったら
無理をしないことが大切
就労移行支援を利用中、「もう辞めたい…」と思うことがあるかもしれません。
よくある理由
- 人間関係がうまくいかない
- 訓練についていけない
- 体調が安定しない
- 就職が決まらない
まずは相談を
辞める前にできること
- スタッフに正直に話す
- 通所日数を減らす
- 訓練内容を調整する
- 一時的に休む
多くの場合、調整することで継続できます。
それでも辞める場合
他の選択肢
- 就労継続支援B型に切り替える
- 別の就労移行支援事業所に変更する
- 一度ゆっくり休んで、準備が整ってから再開する
辞めることは失敗ではありません。自分に合った道を見つけることが大切です。
まとめ
就労移行支援の流れについて、重要なポイントをまとめます:
2年間の流れ
- アセスメント → 基礎訓練 → スキルアップ → 就職活動 → 定着支援
- 一人ひとりのペースに合わせて進む
- 焦らず、着実にステップアップ
各段階で大切なこと
- 最初は生活リズムの確立
- 基礎的なスキルをしっかり身につける
- 自己理解を深める
- 実践的な訓練で自信をつける
就職後も続くサポート
- 6ヶ月間の定着支援
- 困った時の相談先がある
- 「働き続けること」を目指す
自分のペースで大丈夫
- 早く進む人もいれば、ゆっくりの人もいる
- つまずいても、調整しながら進める
- 「働きたい」という気持ちがあれば、道は開ける
就労移行支援の2年間は、決して楽な道のりではありません。でも、多くの人がこの制度を使って、一般企業での就職を実現しています。
あなたの「働きたい」という気持ちを、就労移行支援がきっと後押ししてくれるはずです。
※注意事項 この記事の内容には誤りがある可能性があります。実際のサービス利用を検討される際は、お住まいの市役所・区役所の障害福祉担当課や各事業所で、最新の正確な情報をご確認ください。
就労移行支援の流れを知ることで、利用への不安が少しでも軽くなれば嬉しいです。一歩ずつ、一緒に前に進んでいきましょう。