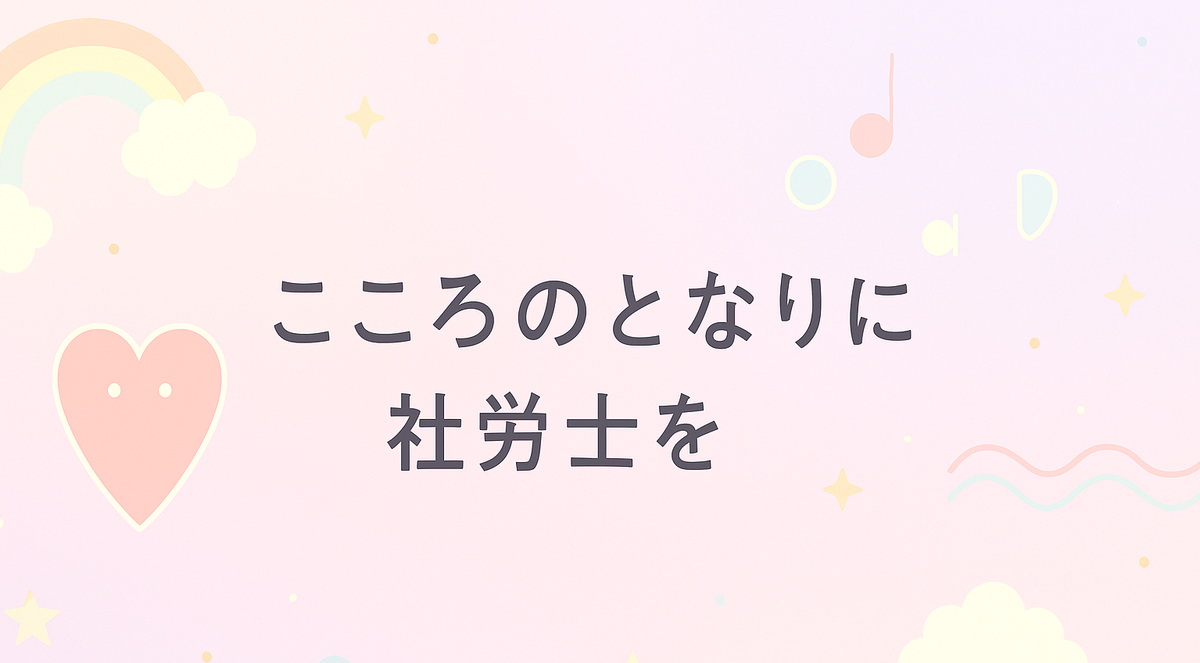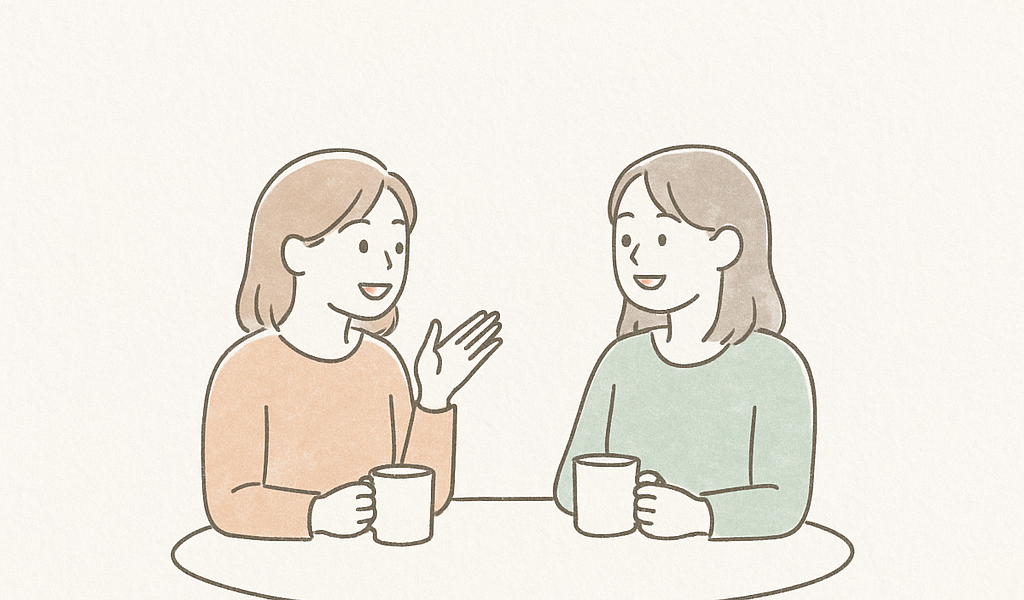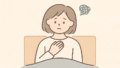働き方を考える時期
最近、友人との間でよく出る話題があります。「パートで働くか、そろそろ正社員などフルタイムで働くか」。
それぞれ子どもたちが大きくなってきて、自分のことを考える時間ができたこと。そして、子どもたちの将来のことを考えてお金を貯めたいと思う時期なんだと思います。
友人Aの悩み:130万円の壁
先日、友人Aと話した際に、数カ月前からパートを始めたと教えてくれました。でも、人手が足りないからもう少し勤務を増やしてほしいと言われたそうです。
ところが、これ以上働いたら、ほんの少し年収130万円を超えてしまう。そうなると、自分で社会保険に加入しないといけなくなるから悩んでいるとのこと。
※その職場は数人の小規模のところだそうで、2024年10月からスタートした新たな社会保険適用対象には含まれないそうです。
友人Bの経験:付加給付の恩恵
また別の友人Bとも、働き方の話をもう何年もしていました。「社会保険の扶養を外れて、新たなチャレンジをしてみてもいいよね」。働き損と言っても、将来もらえる厚生年金も若干増えるし、と前向きに考えていました。
でも、その矢先、友人Bに病気が発覚したのです。検査、入院、手術で、ものすごくお金がかかると教えてくれました。
そして、友人Bはご主人の扶養のままだったので、ご主人の加入している健康保険組合の付加給付のおかげで、月に数万円で済んだそうです。「もし自分で社会保険に加入していたら、付加給付を受けられなかったから、扶養のままでよかった」。そう言っていました。
もちろん、そのご主人が大企業で働かれているからだと思います。でも、この「付加給付」という制度、私も詳しくは知りませんでした。
付加給付とは?
付加給付とは、健康保険組合が独自に行っている給付制度です。国の高額療養費制度に上乗せして、さらに医療費の自己負担を軽減してくれる制度なんです。
**すべての健康保険組合にあるわけではありません。**主に、大企業の健康保険組合などが独自に実施しています。
例えば、月の医療費が高額になった場合、国の高額療養費制度で自己負担額が一定額になりますが、付加給付がある健康保険組合では、さらにその負担額が少なくなることがあります。
フルタイムで働くことは素晴らしい
もちろん、フルタイムで働こうという前向きな行動には、賛成です!それには価値があるし、ボーナスや将来の退職金をもらえたりという楽しみも増えます。自分のキャリアを積んでいくことは、素晴らしいことです。
でも、もし扶養を外れて、ご自身で社会保険に加入するかどうか微妙なラインの金額だったりした場合は、一度、ご主人の加入されている健康保険組合のホームページを見てみてください。高額医療のこと、付加給付のことを、少し調べてみてもいいかもしれません。
知らないと損をすることも
私も友人の話を聞くまで、付加給付について詳しく知りませんでした。知らないと、判断材料が少なくなってしまいます。「扶養を外れて働く」という選択をする前に、一度調べてみる価値はあると思います。
もちろん、お金だけが全てではありません。やりがいのある仕事をしたい、キャリアを積みたい、経済的に自立したい。そういう気持ちも、とても大切です。
でも、家族の健康状態や将来のリスクも考えて、総合的に判断する。そのための情報として、付加給付のことも知っておいてほしいと思います。
ご主人の会社の健康保険組合のホームページを見てみてください。「付加給付」「一部負担金」「高額療養費」などのキーワードで検索すると、情報が見つかるはずです。もしくは、健康保険組合に直接問い合わせてみるのもいいと思います。
働き方は、人それぞれ
130万円の壁を超えるか超えないか。扶養に入ったままか、自分で社会保険に加入するか。正解は、人それぞれです。その人の状況、家族の状況、将来の計画によって、ベストな選択は変わります。
友人たちとの会話から、働き方について改めて考えさせられました。扶養を外れて働くことは、素晴らしい選択です。でも、その前に、付加給付のような制度についても知っておくと、より良い判断ができるかもしれません。
これから働き方を考える方の参考になれば嬉しいです。
※この記事は個人の経験と一般的な情報をもとに書いています。詳しい制度の内容や、ご自身の状況に合わせた判断は、専門家や健康保険組合にご確認ください。