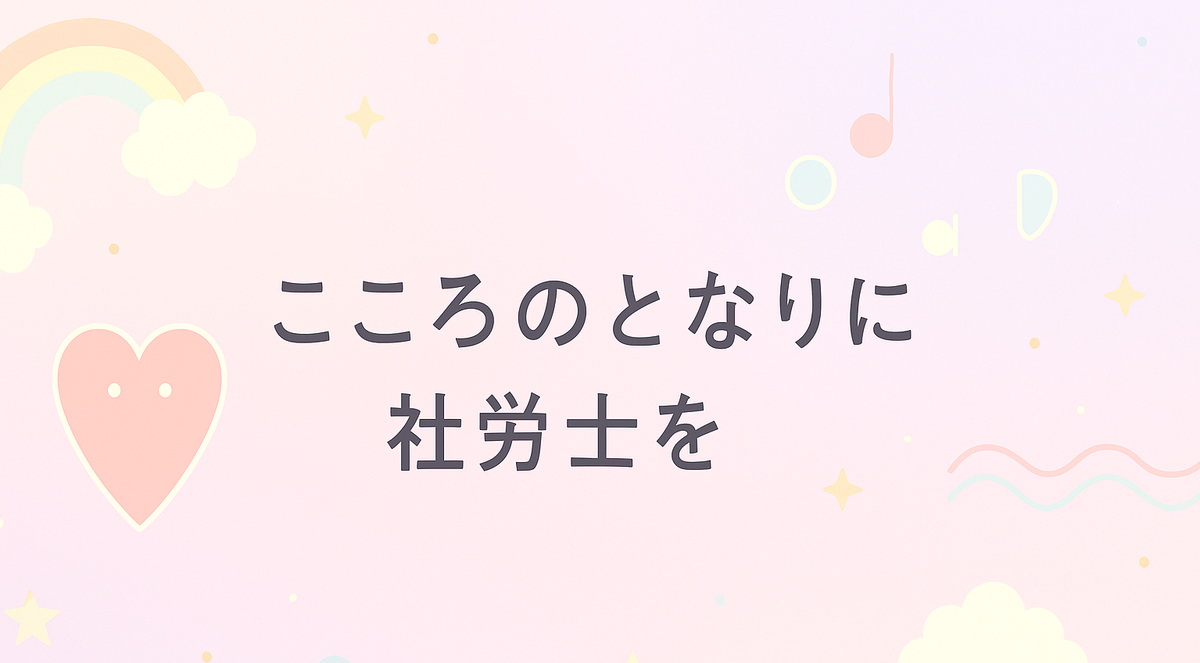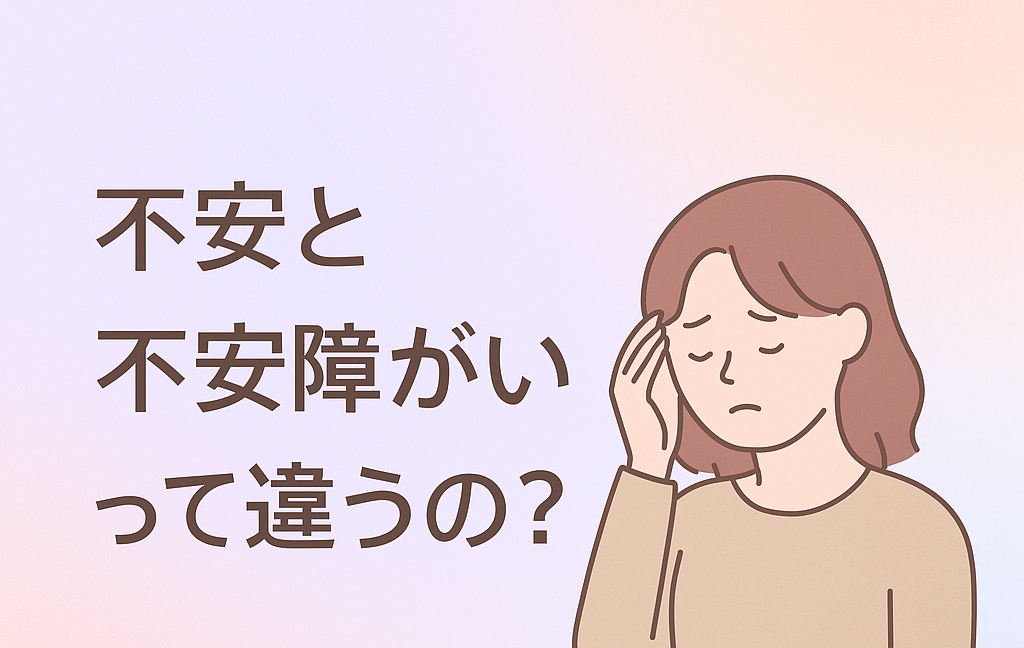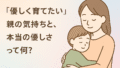はじめに
私たちは日常生活の中で、様々な「不安」を感じることがあります。明日の会議のプレゼン、上司に怒られるかもしれない恐れ、自分や家族の体調への心配…これらは誰もが経験する自然な感情です。
しかし、「不安障がい」を抱える人が感じている不安は、私たちが日常的に経験する不安とは根本的に異なるものです。今日は、その違いについて考えてみたいと思います。
私たちが感じる「普通の不安」
特徴
- 明確な原因がある:「明日のプレゼンがうまくいくか心配」
- 一時的なもの:原因が解決されれば不安も消える
- コントロール可能:深呼吸や準備で軽減できる
- 日常生活への影響は限定的:不安があっても普通に生活できる
例
- 試験前の緊張
- 初対面の人と会う時のドキドキ
- 仕事でミスした後の心配
- 大切な人との別れへの不安
これらの不安は、人間として自然で健康的な反応です。むしろ、適度な不安は私たちが危険を回避し、準備を整えるために必要な感情でもあります。
不安障がいの人が抱える不安
特徴
- 明確な原因がない場合が多い:「なぜかわからないけど不安」
- 継続的で強烈:毎日、長時間続く
- コントロールが困難:理性では「大丈夫」とわかっていても止められない
- 日常生活に大きな支障:仕事、学校、人間関係に影響する
身体症状を伴うことも
- 動悸、息切れ
- 発汗、震え
- めまい、吐き気
- 頭痛、肩こり
具体的な違いの例
普通の不安のケース
状況:明日、上司に叱られそうな予感がある
反応:
- 前日の夜は眠りにくい
- 胃が少し痛む
- でも朝になれば気持ちを切り替えられる
- 実際に叱られても、その後は気持ちが楽になる
不安障がいのケース
状況:特に理由はないが、漠然とした不安が続く
反応:
- 毎朝起きた瞬間から不安
- 「今日は何か悪いことが起きるかも」という恐怖
- 心臓がバクバクして息が苦しい
- 理由を説明できないため、周りに理解されない
- 一日中、この状態が続く
私たちができること
1. 違いを理解する
不安障がいは「気持ちの問題」や「甘え」ではありません。脳の機能に関わる医学的な状態です。
2. 簡単なアドバイスは控える
「考えすぎだよ」「気にしすぎ」といった言葉は、当事者をさらに追い詰めてしまうことがあります。
3. 安心できる環境を作る
- 急かさない
- 批判しない
- その人のペースを尊重する
- 「いつでも話を聞くよ」という姿勢を示す
4. 専門的な支援を勧める
症状が深刻な場合は、医療機関や専門のカウンセラーへの相談を勧めることも大切です。
当事者の方へ
もしあなたが不安障がいで苦しんでいるなら、一人で抱え込まないでください。
- あなたの感じている苦しみは本物です
- 治療や対処法があります
- 理解してくれる人は必ずいます
- 少しずつでも、症状は改善できます
おわりに
不安障がいを抱える人の苦しみは、外からは見えにくいものです。だからこそ、私たちが理解を深め、支え合うことが大切です。
「普通の不安」と「不安障がい」の違いを知ることで、困っている人により適切なサポートができるようになります。そして、誰もが安心して生活できる社会を作っていくことができるのです。
一人ひとりの小さな理解が、大きな支えになります。