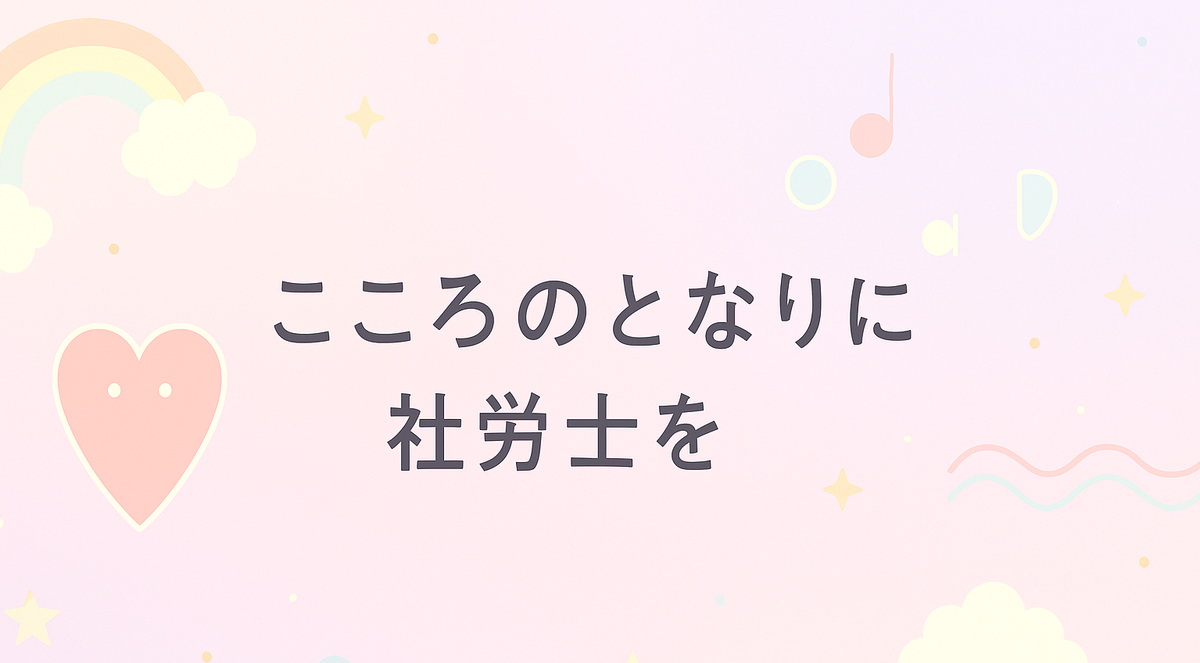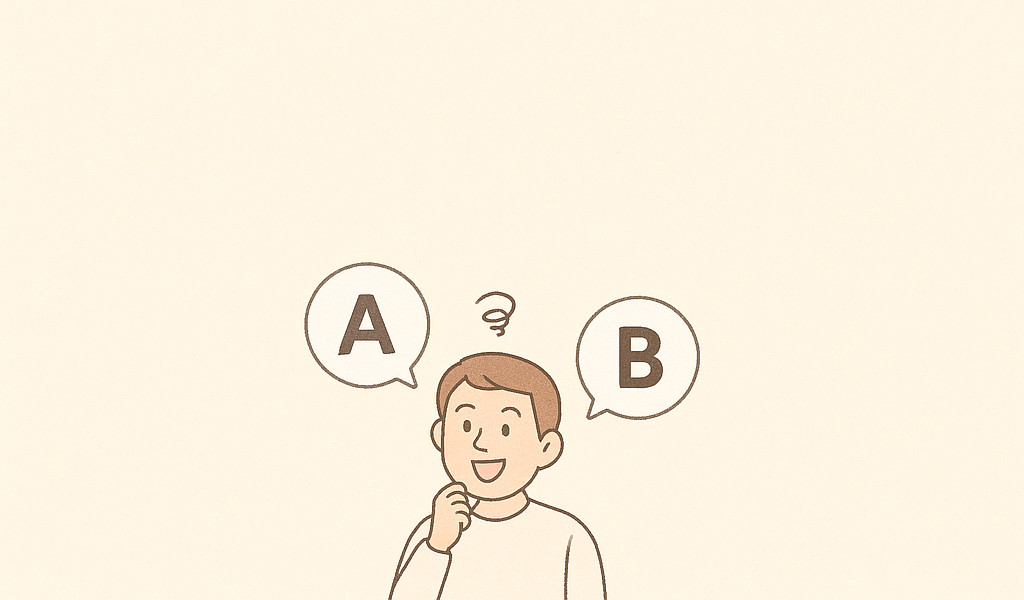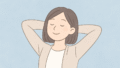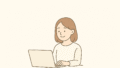就労継続支援A型・B型は、障がいのある方が働くための大切な制度ですが、**A型は雇用契約を結んで最低賃金を受け取る「雇用型」、B型は雇用契約なしで工賃を受け取る「非雇用型」**という根本的な違いがあります。2024年から2025年にかけて制度改正が行われており、新しい「就労選択支援」制度も2025年10月から始まる予定です。
この記事では、どちらが自分や家族に適しているかを判断するための具体的な情報をお伝えします。
働き方の基本的な違い
A型(雇用型)の働き方
A型では事業所と雇用契約を結んで働くため、法的には一般企業で働くのと同じ「労働者」の立場になります。1日4〜8時間、週20時間以上の勤務が基本で、多くの場合は週5日、午前9時半から午後3時頃まで働きます。
実際の利用者の声では「一般企業と違って、障がいへの理解があり、自分のペースで成長できる環境で働けている」という評価が多く聞かれます。作業内容はデータ入力、商品の組み立て・梱包、カフェでの接客、ウェブサイトの管理など多岐にわたります。
B型(非雇用型)の働き方
B型では雇用契約を結ばずに作業に参加するため、「利用者」という立場です。1日2〜4時間程度から始められ、週1日からでも利用可能で、体調や障がいの状況に合わせて柔軟に調整できます。
利用者からは「体調に合わせて参加できるので、病院通いをしながらでも続けられている」「家と病院以外に居場所ができて、少しずつ社会とのつながりを取り戻せた」といった感想が寄せられています。
工賃・給与の現実的な違い
A型の給与水準
A型では最低賃金が保障されており、2024年の実績では月平均8万3,551円を受け取っています。地域により差があり、都市部では月額10万円を超える場合もある一方、地方では6万8,000円程度の場合もあります。
雇用契約により雇用保険にも加入でき、労働者としての権利が保護されます。ただし、施設利用料として月数千円の自己負担が発生する場合もあります。
B型の工賃水準
B型の工賃は月平均1万7,031円(2024年実績)と、A型に比べて大幅に低くなっています。ただし地域や施設により大きな差があり、優良な施設では月4万円以上支払うところもある一方、月数千円程度の施設も存在します。
時間単価で見ると平均243円程度ですが、「お小遣い程度でも、働いている実感と社会参加ができることに意味がある」と考える利用者や家族も多くいます。
利用条件と対象者の違い
A型の利用条件
A型を利用するには原則18歳以上65歳未満で、以下のいずれかに該当する必要があります:
- 特別支援学校を卒業後、就職活動をしたが一般企業への就職に結びつかなかった方
- 就労移行支援を利用したが、一般就労できなかった方
- 一般企業で働いた経験があるが、現在は雇用されていない方
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方
最も重要なのは、週20時間以上の雇用契約を維持できる体力と意欲があることです。
B型の利用条件
B型は年齢制限がなく、より広範囲の方が利用できます:
- 年齢や体力の面で雇用が困難になった方
- 就労移行支援やA型での就労に結びつかなかった方
- 50歳以上の方
- 専門的なアセスメント(評価)により、雇用が困難と判断された方
健康状態や障がいの程度に関わらず、「働きたい」という気持ちがあれば利用可能なのがB型の特徴です。
それぞれのメリット・デメリット
A型のメリット・デメリット
メリット:
- 安定した収入:最低賃金保障により生活基盤が安定
- 就職への準備:雇用契約の経験が一般就労への足がかりになる
- 社会保険:雇用保険加入により退職時の保障あり
- スキル向上:実際の仕事を通じて専門技能を身につけられる
デメリット:
- 出勤義務:体調不良でも契約上の義務があり、柔軟性が限られる
- 仕事のプレッシャー:生産性や品質への要求がある
- 利用条件が厳しい:健康状態や能力面での要件をクリアする必要がある
B型のメリット・デメリット
メリット:
- 完全な柔軟性:体調や都合に合わせて参加時間を調整可能
- プレッシャーなし:作業効率や出勤を強制されない
- 幅広い受け入れ:障がいの程度や年齢に関わらず利用可能
- 無期限利用:利用期間の制限がない
デメリット:
- 収入の低さ:工賃だけでは自立した生活が困難
- 就職への準備不足:雇用契約の経験がないため一般就労への移行が難しい場合がある
- 社会保険なし:雇用保険などの保障がない
どちらを選ぶべきかの判断基準
A型を選ぶべき方の特徴
健康面:
- 定期的な通院はあっても、基本的に体調が安定している
- 週4〜5日、1日4時間以上の作業に参加できる体力がある
- 薬物療法などにより症状がコントロールされている
能力面:
- 基本的なコミュニケーションができる
- 簡単な指示を理解し、作業を継続できる
- 以前に働いた経験があるか、働くことへの明確な意欲がある
生活面:
- 規則正しい生活リズムを維持できる
- 将来的に一般就労を目指している、または安定した収入を必要としている
B型を選ぶべき方の特徴
健康面:
- 体調に波があり、定期的な通院や入院が必要
- 疲れやすく、長時間の作業が困難
- 病状により作業能力が日々変動する
能力面:
- 働いた経験がなく、基本的な作業習慣から身につけたい
- コミュニケーションや対人関係に不安がある
- ゆっくりと自分のペースで技能を習得したい
生活面:
- 家庭の経済的支援があり、工賃の低さが大きな問題にならない
- 社会参加や生きがいを重視し、収入は二の次と考えている
2024年〜2025年の最新制度変更
2024年4月の報酬改定
A型の変更点: 工賃水準や労働時間に応じた評価制度が強化され、より長時間働ける利用者を受け入れる施設により多くの報酬が支払われるようになりました。これにより質の高い支援を行う施設がより運営しやすくなっています。
B型の変更点: 工賃の計算方法が変更され、利用頻度の低い方でも受け入れやすい制度に改善されました。ただし、1日4時間未満の利用者が半数以上いる施設では報酬が30%減額されるため、施設選びの際は確認が必要です。
2025年10月の新制度「就労選択支援」
最も大きな変化として、2025年10月から「就労選択支援」制度が始まります。これはB型を新たに利用する前に、専門職による1〜2ヶ月間のアセスメント(評価)を受ける制度です。
この制度により、一人ひとりの能力や希望により適した支援が受けられるようになり、「本当はA型が向いているのにB型を選んでしまった」といったミスマッチが減ることが期待されています。
最低賃金の上昇
2024年10月に全国平均最低賃金が1,055円(前年比51円増)に上昇し、A型事業所の運営コストが上がっています。この影響で一部の施設が経営難に陥る可能性があるため、施設選びの際は運営が安定しているかどうかも重要な確認点です。
実際の選択プロセスと注意点
専門相談を必ず活用する
まず最初に市町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談しましょう。これらの専門家は個別の状況を詳しく聞き取り、適切なサービスを提案してくれます。
複数施設を見学・体験する
同じA型・B型でも施設により作業内容、雰囲気、支援の質が大きく異なります。少なくとも2〜3ヶ所は見学し、可能であれば体験利用をしてから決めることが重要です。
見学時のチェックポイント:
- スタッフの利用者への接し方は適切か
- 作業内容は本人の能力や興味に合っているか
- 施設の雰囲気は居心地良いか
- 交通アクセスは問題ないか
- 実際の工賃・給与額は期待に合っているか
段階的移行も可能
B型から始めてA型に移行する、あるいはA型で体調を崩した場合にB型に変更することも可能です。最初の選択が完璧である必要はなく、状況の変化に応じて見直せることを理解しておきましょう。
まとめ
就労継続支援A型・B型の選択は、収入の安定性を取るか、柔軟性を取るかという基本的な選択です。A型は雇用契約により安定した収入を得られる反面、継続的な出勤と作業への責任が求められます。B型は収入は低いものの、健康状態や個人の事情に合わせた無理のない参加が可能です。
**最も重要なのは、本人の現在の状況と将来への希望を正直に評価し、専門家と相談しながら決めることです。**2025年の新制度導入により、より適切なマッチングが可能になりますが、それまでも十分な情報収集と相談により、良い選択ができるはずです。
制度は複雑に見えますが、「働きたい」という気持ちを大切にし、一歩ずつ前進していけば、必ず自分に合った働き方を見つけることができます。
※注意事項 この記事の内容には誤りがある可能性があります。実際のサービス利用を検討される際は、お住まいの市役所・区役所の障害福祉担当課や相談支援事業所などで、最新の正確な情報をご確認ください。