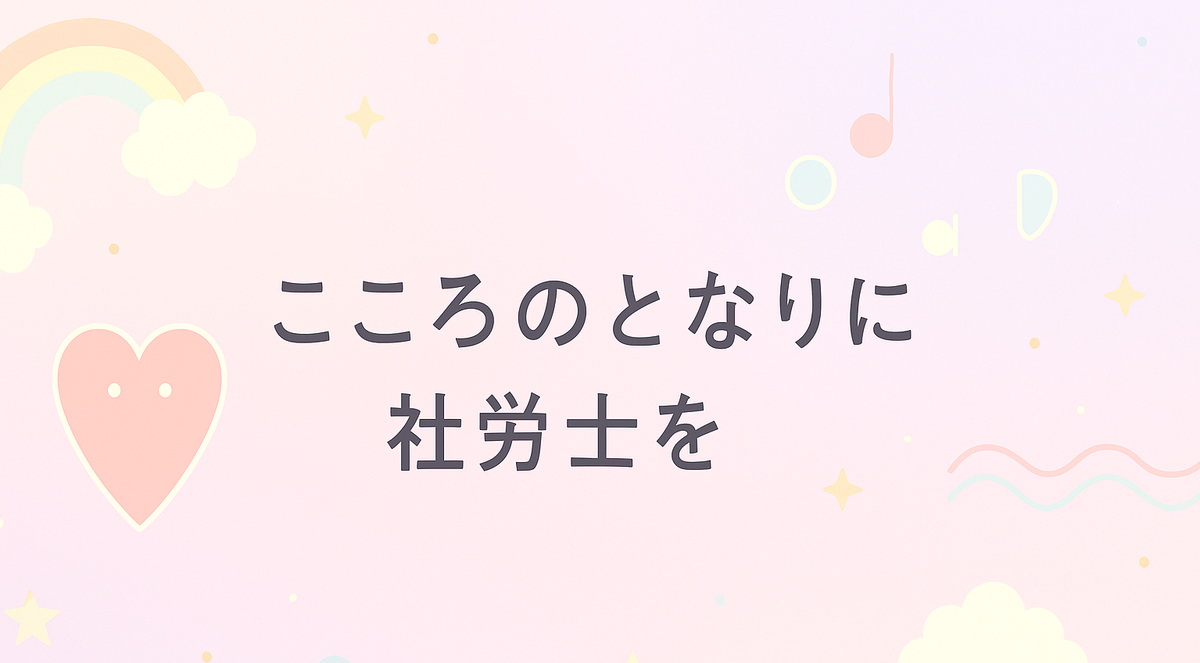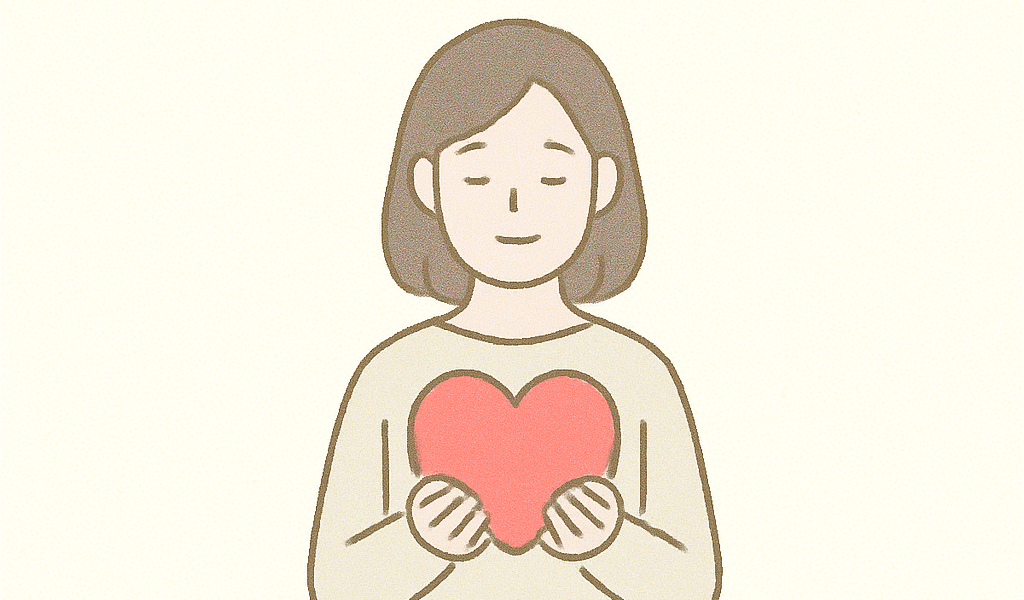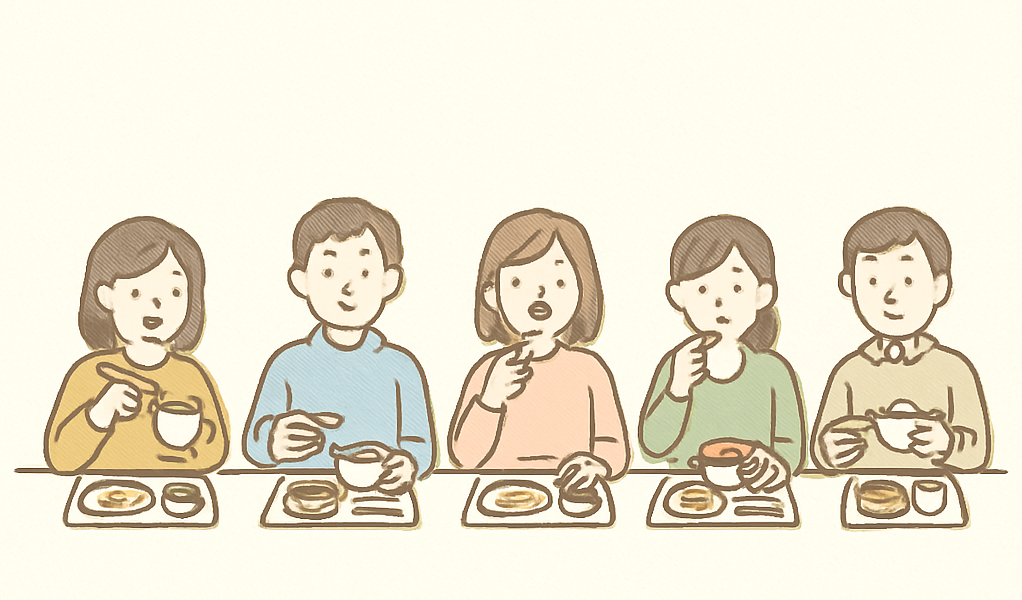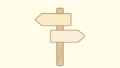人の心に残るのは、特別な言葉や印象的な出来事よりも、「この人といると安心するな」という、ほんの小さな感覚だと思います。
急かさない、待つということ
支援の現場でも、うまく言葉にできない思いを急かさずに待つことがあります。
「どうしたの?」
「何かあった?」
そう聞きたくなる気持ちをぐっとこらえて、ただ隣にいる。
話せるようになるまでの沈黙も、その人にとっては”安心の時間”かもしれません。
言葉にならない気持ちがある。
でも、まだ話せない。
そんなときに、黙って待ってくれる人がいる。
それだけで、心が少し軽くなることがあります。
言葉の奥にあるもの
私は、そんなふうに言葉の奥にある気持ちをそっと見守れる人でありたいと思っています。
「大丈夫です」と言っているけれど、本当は大丈夫じゃない。
「平気です」と笑っているけれど、本当は辛い。
言葉だけを聞くのではなく、その奥にある本当の気持ちに気づけるように。
そして、気づいたときに、そっと寄り添えるように。
静かに心に残る存在
そして、時間がたってからふと思い出したときに、「そういえば、あの人がいてくれたな」と思ってもらえるような存在に。
派手ではなくても、静かに心に残る人でいたいです。
何か特別なことをしたわけではない。
印象的な言葉を言ったわけでもない。
ただ、そこにいてくれた。
ただ、話を聞いてくれた。
ただ、待っていてくれた。
そんな”何でもない”ことが、実は一番心に残るのかもしれません。
こころのとなりで
支援とは、何かをしてあげることではないと思います。
問題を解決してあげることでもない。
ただ、その人の”こころのとなり”にいること。
一歩前に出すぎず、一歩後ろに下がりすぎず、ちょうど隣に。
必要なときには手を差し伸べられる距離で。
でも、押しつけない距離で。
安心の居場所
「この人といると安心する」
それは、特別なことを言われたわけでも、何かをしてもらったわけでもない。
ただ、そこにいてくれる。
自分のペースを尊重してくれる。
急かさないでくれる。
判断しないでくれる。
そんな”何もしない優しさ”が、安心を生むのだと思います。
待つことの力
支援の現場では、「待つ」ことがとても大切です。
すぐに答えを出そうとしない。
すぐにアドバイスしようとしない。
その人が自分で気づくまで、見守る。
その人が自分で決めるまで、待つ。
時間がかかっても、焦らない。
その”待つ時間”の中で、その人の中に何かが育っていく。
それを信じて、そばにいる。
小さな変化に気づく
言葉にならない変化に気づくこと。
少し表情が明るくなった。
少し声のトーンが上がった。
少し視線が合うようになった。
そんな小さな、小さな変化。
それを見逃さずに、心の中で喜ぶ。
でも、大げさに褒めたりしない。
ただ、「気づいてますよ」という気持ちを、静かに伝える。
あなたのペースで
支援する側が、ペースを決めるのではない。
利用者さんが、ペースを決める。
私たちは、そのペースに合わせて歩くだけ。
早く歩きたい人には、少し早く。
ゆっくり歩きたい人には、ゆっくりと。
立ち止まりたい人には、一緒に立ち止まる。
それが、寄り添うということだと思います。
記憶に残る温かさ
人の記憶に残るのは、大きな出来事ではなく、小さな温かさです。
困ったときに、そばにいてくれた人。
話を聞いてくれた人。
何も言わずに、ただ待っていてくれた人。
そんな人のことを、ずっと覚えています。
「あの人がいてくれて、良かった」
そう思ってもらえることが、支援者としての一番の喜びです。
今日も、誰かのとなりで
今日も、誰かの”こころのとなり”で、静かに寄り添っていきたい。
特別なことはできなくても、そこにいることはできる。
言葉がなくても、気持ちは伝わる。
そう信じて、今日も支援の現場に立ちます。
あなたのペースで、あなたらしく。
私は、そんなあなたのとなりで、静かに見守っています。
派手ではなくても、静かに心に残る支援者でありたい。そう思いながら、今日も誰かの”こころのとなり”で。