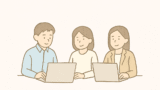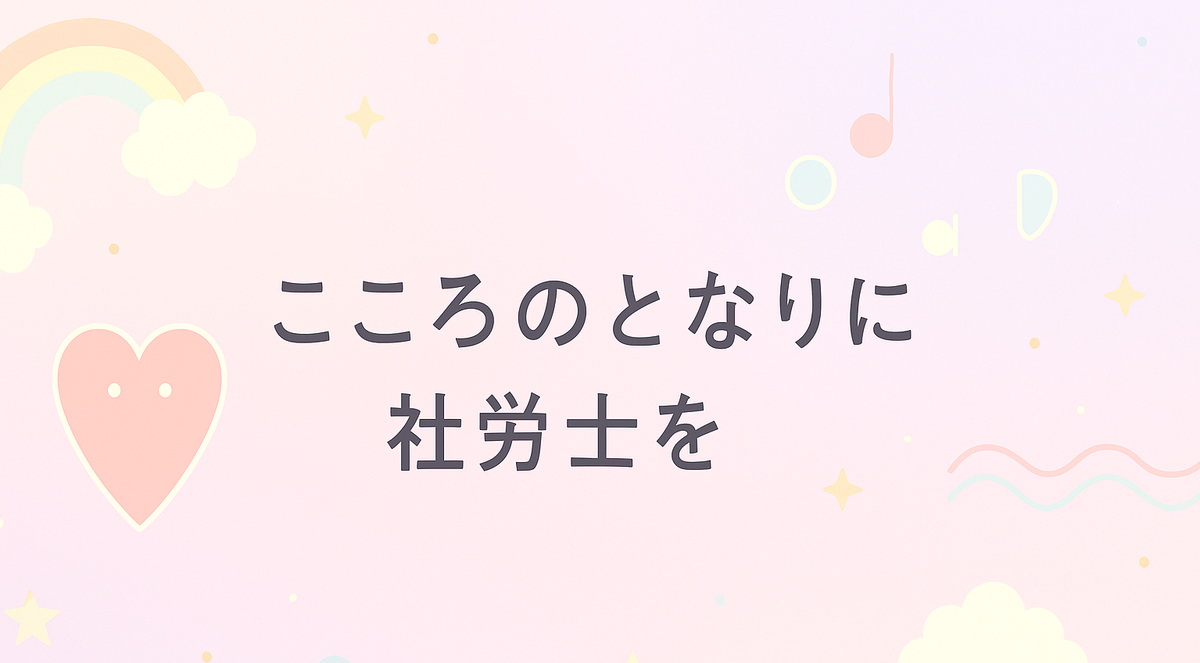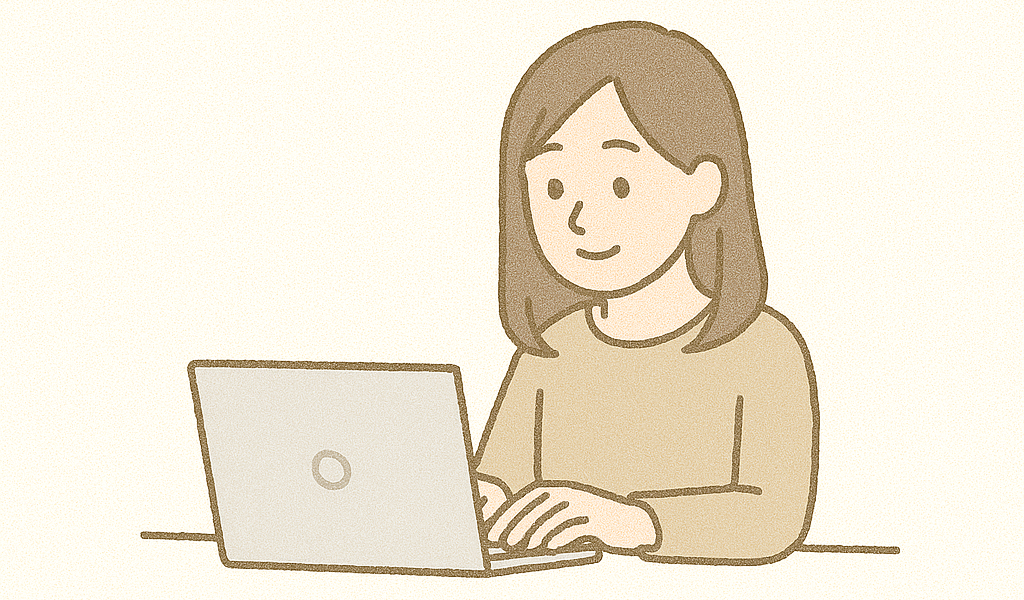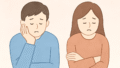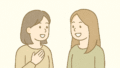はじめに
支援現場で最近直面した、とても難しいケースについて考えたことを書きたいと思います。同じような状況で悩んでいる支援者の方や、当事者の方の参考になれば幸いです。
利用者さんの希望
ある利用者さんから、こんな相談がありました。
「障害者雇用で週2日のデータ入力のバイトを探してほしい。給料は一般の人と同じだけ欲しい。でも、しんどい時は休みたい」
一見すると矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、これはご本人なりの切実な願いでした。
現実とのギャップ
現在の状況を整理すると:
- 就労継続支援B型での工賃:時給200円程度
- 雇用契約での最低賃金:時給1100円程度
- 同じような作業をしていても、約5倍の収入差
ご本人は、この大きな格差に強い不公平感を抱いていました。「自分の能力や努力が正当に評価されていない」という思いです。
一方で、体調が安定せず休みがちという現実もあります。
悪循環の始まり
そして、最も厳しい状況が訪れました。
「工賃だと稼げないから」と事業所に来なくなってしまったのです。
結果として:
- 事業所に来ない → 工賃すら稼げない → さらに困窮 → ますます来られない
完全な悪循環に陥ってしまいました。
この状況の難しさ
ご本人の心理
おそらく、以下のような気持ちが複雑に絡み合っているのではないでしょうか。
- プライドや自尊心の傷つき(「200円の価値しかないのか」)
- 「どうせ頑張っても報われない」という無力感
- 将来への絶望感や焦り
- 体調不良と経済的困窮の悪循環
支援の難しさ
正論を言っても響かない状態です。
「来ないと何も稼げませんよ」 「まずは通所を安定させることが先です」
こうした言葉は、ご本人には「分かってもらえない」と感じられ、かえって距離を置かれる可能性があります。
支援のアプローチ
このような状況で、私たち支援者ができることは何でしょうか。
1. 関係性を取り戻す
- 訪問や電話で「心配している」というメッセージを伝える
- 説得ではなく、今の気持ちを丁寧に聴く
- 「来てほしい」より「どうしたら少しでも楽になるか」に焦点を当てる
2. 小さな成功体験を作る
- 週1回、1時間だけでも来られたら大きな前進
- 工賃以外の価値(仲間、居場所、生活リズム)を再確認してもらう
- 通所できた日は具体的に褒め、認める
3. 現実的な収入面の支援
- 生活保護や各種手当の受給状況を確認
- 緊急的な食糧支援などの福祉サービスにつなぐ
- 家計の見直しをサポート
4. チームでの連携
- 主治医、相談支援専門員、ご家族などと情報共有
- 抑うつ状態など精神面のケアが必要な可能性も
5. 段階的な目標設定
すぐには難しくても、中長期的な道筋を一緒に考える:
- まずは体調を安定させることを最優先に
- 就労継続支援A型(雇用契約あり・最低賃金)への移行を中期目標に
- 出勤率が安定してきたら障害者雇用での週2日勤務へ
支援者として思うこと
このようなケースに直面すると、支援者として無力感を感じることがあります。
「もっと良い方法があるのでは」 「自分の支援が足りないのでは」
でも、大切なのは諦めずに関わり続けることだと思います。
ご本人が「変わりたい」と思えるタイミングは必ず来ます。そのときにすぐ動けるよう、関係性だけは切らさずにいること。それが今、私たちにできることではないでしょうか。
最後に
工賃と最低賃金の格差、体調管理の難しさ、経済的困窮…これらは個人の努力だけでは解決できない、構造的な問題でもあります。
一方で、目の前の利用者さん一人ひとりに、今できる最善の支援を続けていくこと。それが現場の支援者としての役割なのだと、改めて感じています。
同じような状況で悩んでいる支援者の方、当事者の方がいらっしゃれば、ぜひご意見やご経験を聞かせていただきたいです。
※この記事は実際のケースを基にしていますが、プライバシー保護のため、詳細は変更しています。