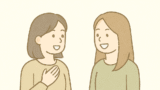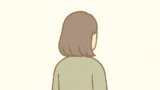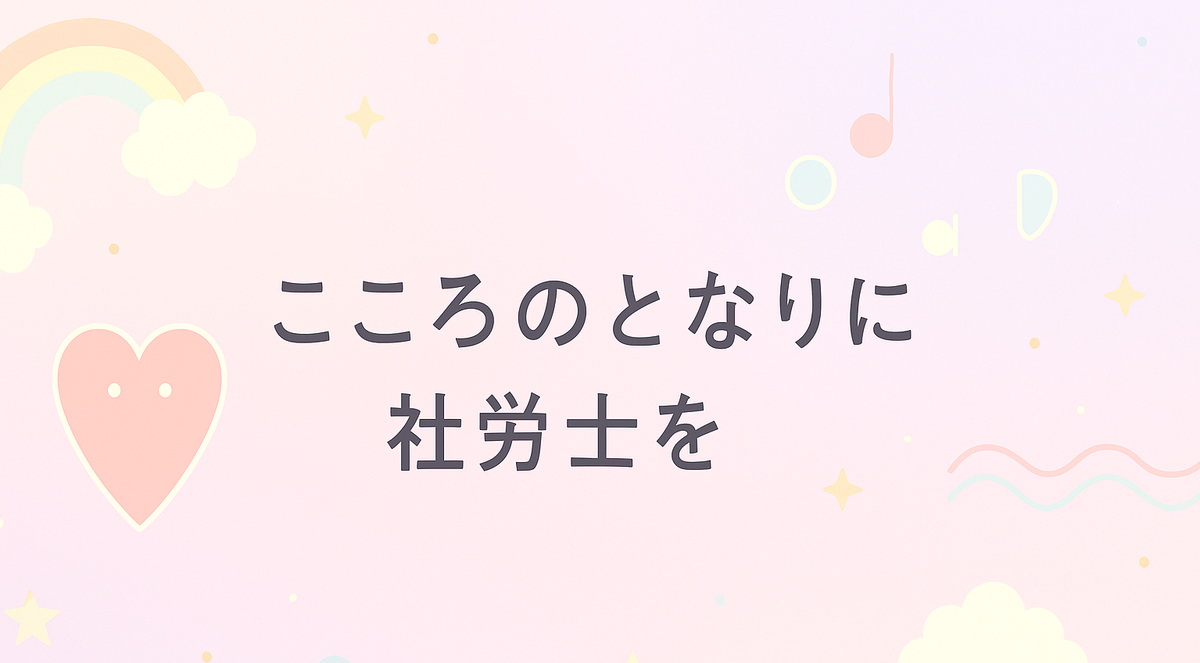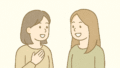先日、外部から委託を受けている作業について、委託元の担当者が視察に来られました。その時の出来事から、コミュニケーションの難しさと支援者としての課題について、考えさせられることがありました。
その時の様子
担当者は利用者さんに、「普段どんなふうに作業を進めてくれていますか?」と質問されました。淡々とした口調で、決して責めているわけではない、ごく普通の質問でした。
でも、利用者さんの表情が少しずつ曇っていきました。受け答えが、だんだんと喧嘩腰になっていく。雲行きが怪しくなってきたのを感じました。
担当者が帰られた後、利用者さんはいつも通りの様子でした。「大丈夫そうだな」。そう思って、私もあまり深く聞きませんでした。
でも、週明け。利用者さんが言いました。「先週から、ずっと腹が立っている」「なぜ怒られているのかわからない」「こっちは作業をして、お礼を言われる側なのに」。
時間差で湧いてくる感情
その場では大丈夫そうに見えても、家に帰って一人になると、考える時間ができます。そして、考えれば考えるほど、よからぬ方向に思考が偏ってしまうことがある。
「あの質問は、責められていたんだ」「自分のやり方が悪いと言われたんだ」「頑張っているのに、認めてもらえない」。感情の整理には、時間がかかります。そして、時には整理がつかずに、モヤモヤが膨らんでしまうこともあります。
なぜ、普通の質問が「責め」に聞こえてしまったのか。利用者さんには、相手に対して斜に構えて考えてしまう癖があるようです。「きっと、何か文句を言いたいんだろう」「自分のやり方がダメだと思われているんだろう」。そう先回りして考えてしまう。だから、受け答えも喧嘩腰になってしまう。
これは、決して利用者さんが悪いわけではありません。過去の経験から、そう身構えてしまうのかもしれません。でも、その癖が人間関係を難しくしてしまうことも、確かです。
支援者としての課題
この癖を、どう伝えればいいのか。「あなたは斜に構えすぎです」と言うのは簡単です。でも、それでは傷つけてしまうだけかもしれない。「相手は責めているわけじゃないよ」と説明しても、「でも、あの言い方は…」と返ってくる。
どう伝えれば、利用者さん自身が気づき、変わっていけるのか。これが、私たち支援者の大きな課題です。
そして、もう一つ伝えなければならないことがあります。事業所は、委託元から仕事を受けて、お金をもらっている立場だということ。利用者さんは「お礼を言われる側」だと思っている。確かに、一生懸命作業をしてくれています。でも、それは「仕事」であり、対価を得ている関係です。この認識のズレを、どう埋めていくか。これもまた、難しい課題です。
「頑張っているのに、認められない」。利用者さんの、この言葉が心に残ります。私たちは、認めているつもりです。追加工賃として、きちんと評価も反映させています。でも、それだけでは足りないのでしょうか?過剰に褒めることが必要なのか?それとも、別の形で承認を伝える必要があるのか?考えさせられます。
コミュニケーションの難しさ
今回の出来事で、改めて感じたこと。コミュニケーションは、本当に難しい。同じ言葉でも、受け取り方は人それぞれ。「質問」が「責め」に聞こえることもある。「確認」が「疑い」に感じられることもある。言葉だけでなく、その背景にある感情や経験が、受け取り方を大きく左右します。
今回、私が反省したのは、その場でのフォロー不足です。雲行きが怪しくなったとき、もっと早く介入すべきでした。担当者が帰られた後、「さっきの質問、責められているように感じた?」と聞いてみる。「あれは、普通の確認だったと思うよ」と、その場で伝える。そうしていたら、週末にモヤモヤを抱えることもなかったかもしれません。タイミングを逃すと、感情は膨らんでしまいます。
私たちにできること
この出来事から、私たち支援者ができることを考えました。何かあったとき、「大丈夫そう」で済ませない。「今の、どう感じた?」と聞いてみる。「相手はこういう意図だったと思うよ」と、別の視点を提示する。押し付けるのではなく、「こういう見方もあるよ」と。
「お礼を言われる側」という認識を、優しく修正していく。「仕事として対価をもらっている」という関係性を、繰り返し伝える。工賃だけでなく、言葉でも態度でも、「見ているよ」「認めているよ」と伝える。でも、過剰にならないバランスを探る。週末を挟んだ後は、特に気にかける。「週末はどうだった?」「何か気になることはない?」と声をかける。
正解はないけれど
この課題に、簡単な正解はありません。一人ひとり、背景も感じ方も違います。でも、だからこそ、私たち支援者は考え続けなければいけない。「どう伝えれば伝わるのか」「どう関われば成長を支えられるのか」「どうすれば、お互いに心地よい関係が築けるのか」。試行錯誤の連続です。
今回の出来事は、私にとって大きな学びになりました。その場でのフォローの大切さ、時間差で湧く感情への理解、認識のズレを埋める難しさ、承認の伝え方のバランス。これらを意識しながら、これからも支援を続けていきます。
完璧にはできないかもしれない。でも、一つ一つの出来事から学び、少しずつ良くしていく。それが、支援者としての成長なのだと思います。
コミュニケーションの難しさと向き合いながら、日々支援を続けています。正解がない中で、試行錯誤しながら、利用者さんと共に成長していきたいと思います。